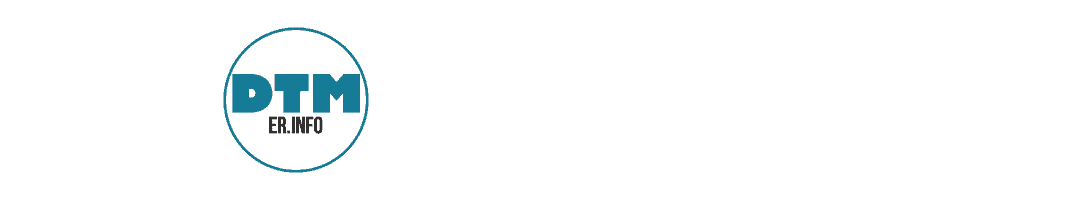- EQなんてどれも一緒でしょ?
- 初心者ははじめにどのEQから導入したらいいの?
このように思っている方は、ひとまず「Pro-Q 4」をさわってみるべきかもしれません。
定番のEQと言えばFabfilter「Pro-Q」が真っ先に名前が上がるほど人気です。最近では、Kirchhoff-EQなど充実した機能を持つ他製品が登場し始めていますが、実際にPro-Q 4を使ってみると、使い勝手の良さにやっぱり素晴らしいEQだなと感じます。
上級者やプロが利用しているところをよくみるため、初心者向けではないイメージもあると思いますが、決してそんなことはありません。むしろ初心者におすすめできる機能がたくさん詰まったEQです。
この記事では、そんなPro-Q 4を実際に使ってレビューしました。導入するメリットから注意点、インストール・アクティベーション方法、使い方まで解説します。
是非、参考にしてください。
1. Fabfilter「Pro-Q 4」とは?
Pro-Q 4は、ミキシングおよびマスタリングに最適化されたイコライザープラグインです。このプラグインは、ゼロレイテンシー、リニアフェーズ、ナチュラルフェーズなどの多彩なモードに対応し、通常のEQモードに加えて、ダイナミックEQ、スペクトラルダイナミクス処理を備えています。作業効率を飛躍的に向上させる多くの機能を搭載しています。
| 開発会社 | Fabfilter |
| 操作画面 |  |
| 価格(定価) | 169ユーロ |
| 主な仕様 | イコライザー |
2. Pro-Q 4とPro-Q 3の違い
Pro-Q 4になり、主に以下のような機能が改善・追加されました。
インスタンスリスト

セッション内のすべてのインスタンスを1つのプラグインインターフェースで管理可能になりました。他のトラックにあるPro-Q 4も別のトラックから調整することが可能です。
スペクトラルダイナミクス

ダイナミックEQをさらに進化させたスペクトラルダイナミクス処理が追加されました。帯域全体のゲインを変更せず、スレッショルドを超えるとその帯域内の特定の周波数をトリガーします。
キャラクターモード追加

アナログ感やビンテージ感を加えるミキシング設定が可能になりました。Clean、Subtle、Warmのいずれかのキャラクターモードを選択できます。
EQスケッチ

直感的な操作で、曲線を直接描くようにEQカーブを作成可能になりました。
オールパスフィルター
フィルター形状に新しくゲインを変えずに位相調整を導入するオールパスフィルターが追加されました。
その他追加機能・改善点
- ダイナミックEQの改善:アタックとリリース設定が追加され、さらに自由なサイドチェーンフィルタリングが可能。
- 分数スロープ設定:3.5 dB/octのローパス/ハイパスフィルターなど、より細かな調整が可能。
- 改善されたダイナミックEQプロセッシング:歪みが少なく、よりクリーンなサウンドを実現。
- リニアフェーズ処理の精度向上:音質をさらにクリアに。
- EQバンドやプリセットのコピー&ペースト:インスタンス間でも簡単に設定を移行可能。
- ゼロレイテンシーとナチュラルフェーズモードの改善
- アナログマッチングが向上。
- パラメータ操作の改善。
- EQコントローラーの値表示部分で直接ドラッグやホイール操作が可能。
3. Pro-Q 4の利点
- 使い勝手抜群
- 調整すべきポイントがわかりやすく初心者にもおすすめできる
使い勝手抜群
使い勝手においては、No.1のEQでしょう。隅々までユーザーの使いやすさを考えて作られていることがよく分かります。
いくつか例を挙げると以下のような点があります。
- 操作性:単純なEQ操作においても、マウスホイールやAlt / Optionキーを活用すると特に使いやすく無駄な動きを減らして調整できます。細かな操作もしやすいです。
- 表示:デフォルトのEQ画面はもちろん、インスタンスリストもパソコン全画面表示にでき、最大限拡大して調整可能です。ノートパソコンなど画面が小さい場合でも、全画面表示で細かく見ることができます。
- インスタンスリスト:インスタンスリストで、全てのPro-Q 4を一つのプラグインから調整できます。
- 鍵盤表示:鍵盤のキーを基準に追加、調整、修正ができます。数値入力して調整する際にもキーを入力して調整できます。
- スペクトラムグラブ:スペクトラムグラブでピークの位置を自動で検出し、調整することが可能です。
- スペクトラルダイナミクス:周波数を全体を調整せずに、周波数内で細かく動的に調整できます。細かな調整なしで細かなEQを動的にかけることができます。
調整すべきポイントがわかりやすく初心者にもおすすめできる
初心者の方には難しい機能もあるかと思いますが、上記で挙げたような機能などを活用することで、調整すべきポイントがわかりやすいです。これをはじめのEQとして、使い方をマスターすることで着実に一歩上の段階に進めると思います。
4. 購入する前に知っておくべき注意点・デメリット
Pro-Q 4は、新しくキャラクターモードが選択できるようになりました。しかし、あくまでクリーンなサウンドを中心とするEQで、他の色付け機能が充実したEQと比べると機能は劣ります。複数トラックで基本はクリーンに使うEQという位置付けが主な用途かと思います。それでも、キャラクターモードがあるだけありがたいです。
また、新機能の中で一番使わないかもと思った機能は「EQスケッチ」です。はじめは便利そうだと思っていましたが、実際使ってみると思ったより使いにくいなと感じました。慣れるまで時間がかかるという点もあるかと思いますが、好きな周波数・ゲイン位置でクリックしてバンド作成した方がやりやすいと今のところ感じています。
5. 口コミ・評判を紹介!
Pro-Q 4の口コミ・評判をまとめました。
人気のEQということもあり全体的に評価はかなり高いです。絶賛するツイートもいくつかありました。
ProQ4 即購入!
早速今日のMIXに使いまくり。
間違いなく今年最強のプラグインです。
話題のProQ4早速導入
この動きやってくれるのはマジでありがたすぎる
Pro-Q 4良き〜
引用:x
6. Pro-Q 4に関するセール情報
Fabfilter製品は、たまにセールをおこないます。
割引率はそこまで高くない場合もありますが、Pro-Qシリーズも過去にはセールの対象になっています。
最新のセール情報はこちらの記事をご覧ください。
 【毎日更新】DTMセール情報まとめ!無料配布やおすすめVSTプラグイン、音源、ブラックフライデー時期も解説!
【毎日更新】DTMセール情報まとめ!無料配布やおすすめVSTプラグイン、音源、ブラックフライデー時期も解説!  【随時更新】FabFilterセール!過去最安値はここ!時期も解説!Pro-Q 4など人気プラグインエフェクト&シンセ
【随時更新】FabFilterセール!過去最安値はここ!時期も解説!Pro-Q 4など人気プラグインエフェクト&シンセ  【随時更新】Pro-Q 4セール!最安値はここ!FabFilter人気の定番イコライザープラグインブラックフライデーも解説
【随時更新】Pro-Q 4セール!最安値はここ!FabFilter人気の定番イコライザープラグインブラックフライデーも解説 7. Fabfilter製品のインストール・アクティベーション方法
Plugin Boutiqueにてインストール・オーソライズ方法が解説されています。
Fabfilterのアクティベーションは簡単で以下のSTEPで完了します。
- Fabfilterにてユーザー、シリアルコードを登録
- ログインしてライセンスコードをコピー
- ダウンロードして起動後、Enter Licenseから貼り付け
8. 使い方を解説
ここからは実際に使い方を解説していきます。英語の公式マニュアルはこちらになります。
https://www.fabfilter.com/downloads/pdf/help/ffproq4-manual.pdf

上部左から
- 一つ前に戻す/一つ先に戻す
- A/B比較
- COPY(A⇄Bにコピー)
- プリセット
- Help
- 全画面表示
があります。表示は全画面以外にも右下からサイズ変更可能です。
上記画像では30dBになっている右上で、3dB/6dB/12dB/30dBから表示する範囲を設定します。範囲外までゲインを上げ下げすると自動で範囲が変更されます。

周波数帯域も下部にある周波数の数字にカーソルを合わしてドラッグもしくはマウスホイールを動かすことで拡大することが可能です。

左下鍵盤マークで周波数に当てはまるキーを見ることができます。
新しいバンドの作り方は主に以下のような方法があります。
- EQライン上にカーソルを置きクリックして上下に動かす
- 好きな周波数、ゲイン位置をクリックする
- ピアノロール上のキーをダブルクリックする
また、Alt / Optionキーを押しながらバンドを作るとダイナミックバンドになります。作ったバンドをAlt / Optionキーを押しながらクリックするとバイパスになります。

バンドにカーソルを合わせるとすぐ近くにそのバンドの情報が現れます。電源ボタンでバイパス、その下で形状変更、ヘッドホンマークでソロモード、バツでバンド削除、右下「▼」から他の詳細設定できますが、バンドを右クリックすることでも以下のパラメータが設定できます。
Disable:バイパス
Invert Gain:ゲインが反転します。
Make Dynamics:ダイナミックモードを作成
Disable Dynamics:ダイナミックモードをバイパス
Clear Dynamics:ダイナミックモードをクリア
Make Spectral:スペクトラルモードを作成
Clear Spectral:スペクトラルモードをクリア
Shape:バンドの形状選択。形状は以下の10種類あります
Bell・Low Shelf・Low Cut・High Shelf・High Cut・Notch・BandPass・Tilt Shelf・Flat Tilt・All Pass
Slope:バンドの傾斜を設定します
Stereo Placement:Stereo、Lef、Right、Mid、Sideを設定します
Split:Stereo・L・Rの場合はLとRに、M・Sの場合はMとSに分かれます。
Delete:バンドを削除します。

バンドを選択すると下にもノブ型のバンドの設定が表れます。バンドを右クリックした時と同じパラメータがあります。QとGainの間にある設定マーク(Bellのみ)は、アナログEQのような互いに影響するQとGainになります。Gainを上げるとQが自動的に少し狭くなり、逆にQが狭くなると少しGainが追加されます。
ノブは上下にドラッグすることで設定できますが、カーソルを合わせてマウスホイールを上下して設定する方法が一番楽です。Shiftを押しながら調整するとさらに細かく調整できます。
ノブをダブルクリックすることで数値を入力できますが、FREQの場合A2やC#2などキーを入力しても反映されます。
リセットはCtrl / Commandキーを押しながら、ノブを1回クリックします。
Dynamic EQ

Bell、Shelf、Tiltなどゲイン調整ができるフィルターではダイナミックEQモードができます。
これは入力に合わせてGainが上下する機能で通常のGainを中心に、最大、最小でDynamic EQのGainまで動きます。
Alt / Optionキーを押しながらバンドを作るとダイナミックバンドになりますが、バンドを選択して真ん中Gainノブの周りにカーソルを合わせて上下することで調整も可能です。調整すると赤くなります。ゲインの変化は、その上に黄色で表示されます。
Dynamic EQは、通常オートモードでGainノブの上部の右矢印をクリックすることで細かく調整できます。
- Threshold:トリガーするスレッショルドを設定できます。最大値に設定するとオートモードになります。
- External Sidchain:バンドと上矢印のようなアイコンは、プラグインの入力信号ではなく外部サイドチェーン信号によって動作します。
- Attack / Release:ダイナミックな変化を適用するスピードを調整します。50%では、オートモードと同じ動作になります。
- Band / Free:トリガーする信号を指定できます。デフォルトはBandで、バンドの周波数帯域に応じてダイナミクス処理がトリガーされます。Freeに設定すると、ローカットとハイカットのフィルタリングコントロールが表示され、トリガーする周波数帯域をカスタマイズできます。
- ヘッドホンマーク:現在のトリガー信号を聴くことができます。
Gainノブの上部には他にも電源ボタンでBypass、「×」でダイナミックEQモードをクリアします。
Spectral Dynamics

Pro-Q 4で、Spectralモードが追加されました。帯域全体のゲインを変更せず、スレッショルドを超えるとその帯域内の特定の周波数をトリガーします。
Gainノブの上部のスペクトルマークを選択することでSpectralモードとなり、Dynamic EQと同じように設定できます。また、Alt / Option+Shift+クリックで、EQディスプレイ内に直接Spectralバンドを作成することもできます。また、バンドを右クリックしたメニューからMake Spectralを選択することでもスペクトラルバンドを作成できます。
Gainノブの上部の右矢印をクリックすることでDynamic EQと同様に細かく調整できます。以下のSpectralモードのみのパラメータがあります。
Spectral Density:スペクトル処理をどの程度選択的に行うかを設定します。低い場合、周波数に対してトリガーされる範囲は比較的広くなり、高い場合、範囲が非常に狭く特定的なものになります。
EQ Sketch

EQ Sketchは、その名の通りスケッチするように線を描いてEQの線を描いていくモードです。左下のペンマークを選択してドラッグして描くことができます。細かく詳細に設定する前の、とっかかりとして素早く簡単なEQラインを作成できます。
Character Mode

下部の右側に、新しいキャラクターボタンがあります。このボタンを使って、Clean、Subtle、Warmのいずれかのキャラクターモードを選択できます。
- Clean:デフォルトのモードで、Pro-Qで知られるオリジナルの透明感のあるサウンドです。
- Subtle:ビンテージタイプのサチュレーションを微妙に導入します。カラーリングの量はプログラムに大きく依存し、周波数ごとに異なり、EQバンドにも影響されます。
- Warm:真空管のようなサチュレーションと色彩感のあるサウンドが得られます。
Processing mode

Pro-Q3には3つのモードが下部から選べます。
Zero Latency
その名の通りゼロレイテンシーなモード。アナログの振幅応答と可能な限り一致させて、レイテンシーを無くします。
Natural Phase
アナログの振幅応答に一致するだけでなく、位相も一致させます。そのため、目立つ※プリリンギングや長いレイテンシーが生じることなく、低い周波数と高いQ設定でも、正確な周波数応答と最高の音質を実現します。
Linear Phase
オーディオの大きさのみを変更し、位相はそのままにするモード。ただし、Linear Phaseフィルターにはいくつかの欠点があります。まず第一に、レイテンシーが発生します。プラグインを通過するときに信号全体が遅延します。処理解像度を高くすると、レイテンシーが長くなり、トランジェント(キックドラムなど)がエッジを失う可能性のある※プリリンギングが発生することもあります。Linear Phaseでは、処理解像度ボタンが使用可能になります。
※プリリンギングとは?
位相ずれをなくしたリニアフェイズEQなどで、発生する副作用。アタックが不鮮明になります。
Instance List

下部の中央にある名前(現在のトラックの名前)をクリックすると、他のトラックに使っているPro-Q 4も一覧で表示されます。上部のズームスライダーや隣のオートズームマークを使って拡大・縮小できます。また、Searchに入力して、表示されているインスタンスを簡単にフィルターすることができます。
Pro-Q 4それぞれの通常インターフェースのようにクリックやドラッグでカーブを作成、調整することができます。新機能のEQ Sketchを使用することも可能です。
ピンマーク:それぞれのインスタンス左上のピンマークからピン留めでき、上部のピンマークからピン留めされたトラックのみを表示することができます。
出力ボタン:それぞれのインスタンス右下に小さな出力ボタンがあります。カーソルを置くと、バイパス、オートゲイン、位相反転、出力レベル/パンニングなど、インスタンスの出力設定にアクセスできます。また、上部の音量+ボタンをクリックすることでインスタンスのレベルが一瞬上がり、どのトラックで作業しているのかをすぐに分かります。
メニュー:それぞれのインスタンス中央右にあるメニューボタンから、コピー、ペーストやEQ Matchの開始など、さまざまなオプションにアクセスできます。
赤い丸マーク:それぞれのインスタンス左上のピンマーク隣にあるクリックすると赤くなる丸マークは、被りを検出することができます。クリックすることで、そのインスタンスと被りがある他のトラックの帯域が赤く表示されます。
Analyzer Panel

下部のAnalyzerから、アナライザーの設定ができます。範囲(Range)、解像度(Resolusion)、リリース速度(Speed)、Tilt(勾配)が設定できます。
Pre / Post / Ext:プリ、ポスト、外部EQスペクトラムの視覚化を有効または無効にします。Extボタンのメニューを使用すると、メインのEQディスプレイで外部スペクトルを選択することができます。これはプラグインの外部サイドチェーン、または他のPro-Q 4インスタンスのポストEQスペクトルがリストとして表示されます。
Spectrum Grab:帯域矢印マークで表されているSpectrum Grabを有効にした場合、マウスを数秒間スペクトラムの上に置いたままにすると、Pro-Qは自動的にスペクトラムグラブモードに入ります。スペクトラムがフリーズする間、既存のEQバンドは暗くなります。これで、白い出力線のピークの1つをつかんで、ドラッグして調整できます。
Show Collisions:帯域ハイライトマークで表されているShow Collisionsは、周波数のかぶり表示を有効または無効にします。かぶりは赤く表示されます。
Freeze:スペクトルの下降が止まり、時間の経過とともに最大値が蓄積されます。Freezeが有効になっている間は、下部のAnalyzerボタンの上部に青い線が表示され、この状態を示します。
スペクトラムグラブとは?

音を再生し、鳴っている周波数部分にカーソルを合わせることで紫色になりピーク位置を確認でき、ドラッグして調整できる機能です。これはかなり便利で、左下からピアノロールを出すとピークのキーがわかります。デフォルトでオンの状態です。スペクトラムグラブモードでは、ベルフィルターのみが作成され、適切なQが自動的に決定されます。
ハイライトが青色になるまでスペクトラム領域を長押しすることにより、永久スペクトラムグラブモードをアクティブにすることもできます。これはスペクトラムが永久にフリーズされるため、複数のスペクトラムピークをつかんでドラッグできます。
このモードを終了するには、白い曲線ではなく、ディスプレイの背景をクリックするだけでOKです。
EQ Match
EQ Matchは、Instance Listの各インスタンス右側のメニューから選択できるようになりました。これはある音と同じような特性にしたい場合に利用します。
以下の2ステップで完了します。STEP 1で元となる音の型をとって、STEP 2でEQを適応させたい音にマッチさせます。
STEP 1.リファレンススペクトラムを作成

EQ Matchを選択し再生すると、すぐに分析を開始してスペクトラムが構築されます。Referenceをクリックしてインプット、サイドチェーンやOther Instanceで他のインスタンスなどを選択できますし、Save Input As Reference Spectrumでスペクトラムをセーブすることも可能です。
STEP 2. マッチ

セーブしたリファレンスや信号を選択してMatchボタンをクリックすると、一致させるために必要なEQバンドの数と種類を自動的に計算します。 スライダーでバンドの数を調整し、Finishで完了します。
Output options

右下からアウトプットの設定が可能です。アウトプットの左にある四角マークはバイパスになります。
二重のノブの内側でアウトプットのゲイン、外側でパンを調整できます。ノブ左下のLRをMSに変えることでMSのゲインバランスを調整することも可能です。
下のボタンは左から、Phase Invert(位相反転)、Auto Gain、アウトプットメーター表示非表示です。
ボタンとノブの間にあるメーターはGain Scaleで全てのゲイン量まとめて調整可能です。
まとめ
Pro-Q 3は初心者から上級者まで利用できる使い勝手の良いEQです。
きっと長い目線であなたの音楽制作のお供となってくれることでしょう。
実際に使ってみると人気であることも十分に理解できます。
初心者の方は、はじめはなれない部分もあると思いますが、勉強しながら長いスパンで使いこなしていくことで、作曲家としてレベルアップすることができます。
この記事が参考になれば幸いです。
質問等ございましたらコメント欄からどうぞ!