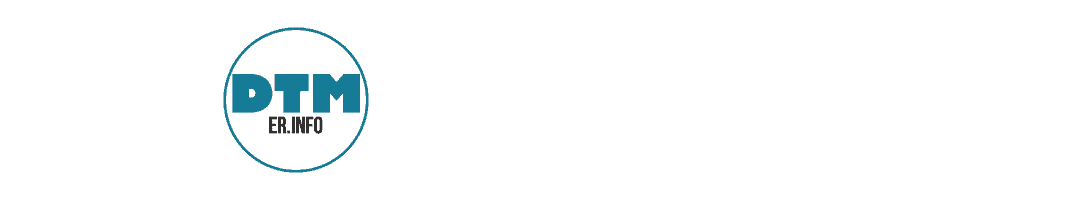ミュージシャンなら知っておくべき、「音圧」について考えます。
Spotify、Apple Music等ストリーミングサービスやYouTubeなどの投稿サイトでは、一定以上の音圧に設定すると音量が下げられる場合があります。
- エンジニアさんはもちろん知っていると思いますが、このことを認知しているミュージシャンがどれだけいるでしょうか?
- そもそもダイナミックレンジ(音量差)を犠牲にしてまで最大の音圧を取る必要があるのでしょうか?
実際、プラットフォームに音楽を投稿するのはミックスしてもらった音源を渡されたミュージシャンだったりするので、知っておきたいところです。
まずは作曲ソフト(DAW)を扱ったことがない人向けに音圧を出すということの説明をしたいと思います。
1. 音圧戦争(ラウドネスウォー)とは?

誰しも自分の音源を良い状態で聴かせたいものです。
小さい音よりでかい音の方が迫力がありガツンと刺さる音源になるといったことから音圧戦争が勃発しました。
コンプレッサーで音を圧縮し全体を持ち上げることでピークにひっつくような音源になっていきました。
誰よりも高い音圧を目指して皆が音を潰しまくったのです。。
2. ラウドネスノーマライゼーションとは?
しかしながら、音圧戦争もそう長くは続かないかもしれません。(願望)
その原因の一つはCDからストリーミングへの移行です。
一つのコンテンツとしてパッケージ化されたCDと違い、様々なアーティストが入り乱れるSpotify、Apple Music、Amazon Music、YouTubeなどではそれぞれの楽曲の音量が変わると大変困ります。
そこで導入されているのが『ラウドネスノーマライゼーション』です。
ラウドネスノーマライゼーションとは。LUFS/LKFSという単位をもとにある一定以上は自動で音量を下げる仕組みのことです。
ストリーミングプラットフォームは、リスナーが音楽を連続して聴く際、たとえ異なるアーティスト、アルバム、ジャンルの間で絶えず切り替わっても、スムーズで一貫したリスニング体験をしてもらいたいと考えています。スムーズなリスニング体験を実現するための重要な要素の1つは、連続したトラックの音の大きさ、聴こえ方が同じであることです。これによって、リスナーは音量を調整することなく、音楽を楽しむことができます。
同じLUFSレベルの2つの音楽は、同じ音量として認識されます。そのため、現在ではほとんどのストリーミングプラットフォームが、すべてのオーディオ素材を特定のLUFSレベルに正規化し、連続するトラック間で一貫した知覚ラウドネスを保証しています。
もしCDの頃のように音圧を上げると、本来あったはずのダイナミックレンジ(音量差)を無くしているので下記のような形になります。

LUFSとは?
オーディオの知覚される音圧は、EBU 128標準に従って、LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)で測定されるのが一般的です。LUFSは、オーディオ素材の音圧を測定するプロセスで使われる測定単位です。
音を聞く時、同じ音量でも低音域と高音域では聞こえ方、感じ方がまるで違います。LUFSは、実際の聞こえ方を考慮した知覚的なフィルターと組み合わせたオーディオ素材の平均レベルを経時的に分析します。
LUFSは、測定期間によって3つの値で表される場合が多いです。
- Intergrated:長い観察期間の平均ラウドネスを表します。統合ラウドネス、プログラムラウドネスとも呼ばれます。ストリーミングプラットフォームがトラックのラウドネスについて話すときに参照される値でもあります。EBU 128規格では、長い観測時間でなければ有効な統合ラウドネス測定値を表示することができないことに注意してください。
- Short-term:3秒にわたって計算されます。これは通常、時間とともに変化し、トラックの異なるセクションのラウドネスに関する情報を提供します。
- Momentary:400msわたって計算され、過度にダイナミックなラウドネスのピークを特定するのに役立ちます。
LUFSの設定目安はストリーミングプラットフォームによって変わりますが、下記で紹介しているプラグインsmart:limitでは
- Spotify:-14LUFS
- YouTube:-14LUFS
- Apple Music:-16LUFS
- Amazon Music:-19LUFS
となっています。ただし、ほとんどのストリーミングプラットフォームでは、ある一定の最小ラウドネスしか必要としない点だけご注意ください。
補足:トゥルーピーク(True Peak)も重要
LUFS以外にもトゥルーピーク(True Peak)も設定、調整する必要があります。処理された出力信号の真のピークレベル最大許容値を設定し、0dBFSより低く制限を設定するとピークにある程度のヘッドルームを与えることができます。ストリーミングプラットフォーム用に信号をバウンスする場合は、少なくとも-1dBFSを目安に制限することをおすすめします。
3. おすすめの対策!確認・設定用プラグインソフト
ラウドネスノーマライゼーションは徐々に浸透しており、最近の作曲ソフトDAWの拡張機能VST、AUなどのプラグインエフェクトでは対応しているものも増えています。
おすすめのプラグインとしては
- AI機能搭載リミッターsonible「smart:limit」
- AI機能搭載マスタリング向けマルチエフェクトiZotope「Ozone 11」
などが挙げられます。
sonible「smart:limit」
smart:limitでは、Spotify、Apple Music、Amazon Musicなど各プラットフォームを選択して、AI機能を利用して楽曲を解析し、自動でリミッターを調整してくれます。
それぞれのプラットフォームに合った設定ができるだけでなく、リミッティングの細かな設定も可能でかなり評価の高いリミッタープラグインエフェクト&メーターツールです。
<使い方やレビューなど詳しい記事>
 sonible「smart:limit」使い方やレビュー!AI機能搭載リミッタープラグイン
sonible「smart:limit」使い方やレビュー!AI機能搭載リミッタープラグイン sonible製品一覧 ▶︎Plugin Boutique ▶︎PluginFox ▶︎SONICWIRE ▶︎Audio Plugin Deals ▶︎Best Service ▶︎ADSR Sounds ▶︎楽天 ▶︎Rock oN ▶︎公式
▶︎Plugin Boutique ▶︎PluginFox ▶︎SONICWIRE ▶︎Audio Plugin Deals ▶︎Best Service ▶︎ADSR Sounds ▶︎楽天 ▶︎Rock oN ▶︎公式
iZotope「Ozone 11」
DTMにおいて有名な音圧を上げるマスタリングソフトといえばiZotope「Ozone」でしょう。
Ozone 11はプラグインエフェクトとしてのみ利用できますが、前回バージョンOzone 9はスタンドアローン(単体で起動)にも対応していました。
Ozoneの最大の魅力はAIによる自動マスタリングです。
Ozone 9では、AIによる自動マスタリングでもCDとストリーミングで設定が異なりました。Ozone 11になり、マスターアシスタントでは、2つのラウドネスと出力レベルの最適化設定があります。
- Streaming:ほとんどのストリーミングサービスの典型的な設定です。MaximizerモジュールのTrue Peakが有効で、出力レベルは-1dBに設定されます。
- Full Scale:ほとんどのマスターに適した出力レベルです。MaximizerモジュールのTrue Peakリミッターを無効にして、フルスケールぎりぎりの-0.1 dBに設定されます。
もちろんAI機能だけでなく、各エフェクトも優れており、プロも利用するプラグインエフェクトです。
<使い方やレビューなど詳しい記事>
 Ozone 11使い方とレビュー!プラグインの違い(10やElements・Standard・Advanced) も解説!iZotopeマスタリングエフェクト
Ozone 11使い方とレビュー!プラグインの違い(10やElements・Standard・Advanced) も解説!iZotopeマスタリングエフェクト  Ozone 11の違い(Elements・Standard・Advanced)比較!どれを買うべき?iZotopeおすすめの買い方も解説
Ozone 11の違い(Elements・Standard・Advanced)比較!どれを買うべき?iZotopeおすすめの買い方も解説 
▶︎Plugin Boutique ▶︎PluginFox ▶︎ADSR Sounds ▶︎SONICWIRE ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎Best Service ▶︎サウンドハウス ▶︎MIオンラインストア ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
4. 無料で対策!確認・設定用フリーラウドネスメーター
各ストリーミングや投稿サイトによる違いを確認できるメータープラグインもたくさんあり、無料で利用できるフリープラグインもあります。
Youlean「Youlean Loudness Meter 2」
Youlean Loudness Meter 2は、人気のラウドネスメータープラグインの後継です。VST2、VST3、AU、AAXなどの作曲ソフトDAW用プラグインのみならずスタンドアロンアプリ(DAWなしで起動)も可能です。無料と有料2つのバージョンがあります。
<詳しい記事>
 【無料】「Youlean Loudness Meter 2」無償配布!ラウドネスメーターフリープラグイン最新ベータ版もダウンロード可能
【無料】「Youlean Loudness Meter 2」無償配布!ラウドネスメーターフリープラグイン最新ベータ版もダウンロード可能 APU Software「APU Loudness Meter」
APU Loudness Meterは、APU Softwareが開発するラウドネス分析プラグインです。
このプラグインは、リアルタイムのラウドネス監視とオーディオのラウドネスの時間経過によって変わるヒストグラム解析の両方を提供するように設計されています。様々なパラメータをサポートしており、リアルタイムで調整することができます。
<詳しい記事>
 【無料】APU Software「Loudness Compressor&Meter」無償配布中!ラウドネス範囲を設定するコンプレッサー&時間変化を可視化するラウドネスメーター
【無料】APU Software「Loudness Compressor&Meter」無償配布中!ラウドネス範囲を設定するコンプレッサー&時間変化を可視化するラウドネスメーター Loudness Penalty(Webのみ無料)
Loudness Penaltyという無料でWebにアップロードするだけでどれだけ音量が下げられるか確認できるサイトもあります。
ファイルをアップロードするだけで、それぞれのプラットフォームでどれだけ下げられているかを確認できます。
YouTube、Spotify、Tidal、Pandora、iTunesの5つありWeb版は無料ですが、プラグインとして有料版もあります。
書き出す前にDAW内で確認したい方は有料版も便利です。
5. そもそも音圧は上げるべき?
そもそも全プラットフォームで最大の音圧を取りにいく必要はあるのでしょうか?
ダイナミックスレンジ(音量差)を潰してまで音圧を出す必要があるのでしょうか?
そのあたりの詳しい内容を含めた専門書としてDavid Shimamoto氏の本をおすすめします。
デジタル機器を使った音楽制作の基礎知識を学べるだけでなく、演奏/録音された音楽の魅力について考えさせられる優れた本です。ダイナミック・レンジについての章は、レコード会社のディレクターやロックバンドのメンバーたちこそ一読を!と思いました。
まとめ
まとめると以下のようになります。
- ストリーミングサービスや投稿サイトでは、ラウドネスノーマライゼーションが導入されている場合がある。
- そのためCDとは違う音圧の調整が必要になった。
ただし、そもそも最大音圧を取りにいく必要性があるのか?という問題もあります。
ダイナミックレンジと音圧の狭間でせめぎ合って楽曲が一番良く聞こえる形を模索する必要があります。エンジニアさんに任せっきりではなくミュージシャンの方も音圧としっかり向き合う必要があるかもしれません。
また詳しいラウドネスノーマライゼーションの検証や音圧に関する記事をまとめましたので、もっと深く知りたい方は下記の記事が大変勉強になります。
Studio Gyokimae
「とーくばっく 〜デジタル・スタジオの話〜」の著者であるDavid Shimamoto氏のサイトです。
YouTubeラウドネスノーマライゼーションの検証
Youtubeのラウドネスノーマライゼーションを検証してみた。
ここではエンジニアさんが音圧だけでなくピーク(dBFS)についても検証しております。
ピークも注意しなければいけない点です。
Spotifyラウドネスノーマライゼーション検証
Spotifyのラウドネスノーマライゼーションを検証してみた
Spotifyの場合どの単位(アルバム?1曲?プレイリストは?)でラウドネスノーマライゼーションが行われるのか検証しております。
質問等ございましたら下部のコメント欄からどうぞ!