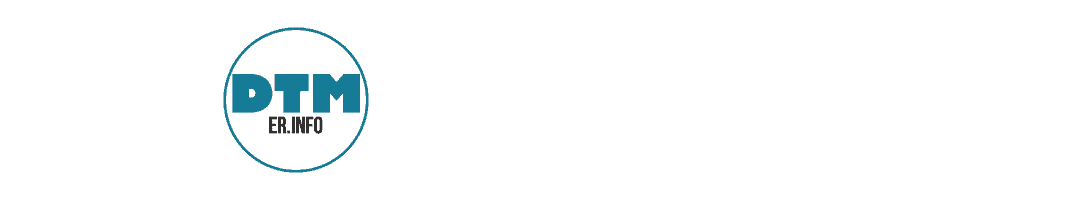AASで一番人気のアナログシンセを再現した音源「Ultra Analog VA-3」。
アナログシンセを再現した太い音でありながら、フィジカルモデリングによって広く音作りできるいいとこ取りなシンセです。
この記事ではそんなUltra Analog VA-3をレビュー。メリットやデメリット・注意点からインストール・アクティベーション方法、使い方まで解説します。
是非参考にしてください。
1. AAS「Ultra Analog VA-3」とは?
Ultra Analog VA-3は、AAS(Applied Acoustics Systems)が開発するバーチャルアナログシンセサイザーです。VA-3は2019年に発売されました。
画像をみるかぎり、Moogモデルかな?と思いますが、実際はフィジカル(物理)モデリングによるバーチャルなアナログシンセサイザーなので特定のモデルを再現したソフトウェアではありません。
Ultra Analog VA-3は、サンプリングやウェーブテーブルを使用せず、受信したコントロールに合わせて演奏しながら音を計算していきます。
作曲ソフトDAWの拡張機能AU(Audio Unit)、VST 2、VST 3、AAXプラグインとして利用できる他に、単体で起動するスタンドアローンにも対応しています。
また、Native Instrumentsのコントローラーなどと連携するNKSにも対応しています。
| 開発会社 | AAS(Applied Acoustics Systems) |
| 操作画面 |  |
| 価格(定価) | 199ドル |
| 主な仕様 | バーチャルアナログシンセサイザー音源 |
サンプリング音源とフィジカル(物理)モデリング音源の違い
サンプリング音源は、サンプルを元に音作りをします。対して、フィジカル(物理)モデリング音源は仮想的に音色をシミュレートして音を作ります。
フィジカル(物理)モデリング音源の製品としては
- ベース音源IK Multimedia「MODO BASS」
- ドラム音源IK Multimedia「MODO DRUM」
- ピアノ音源MODARTT「Pianoteq」
- AAS(Applied Acoustics Systems)製品
などがあります。
仮想的に音色を変えることができるのでこれらのモデリング音源は細かくパラメータを設定できるという特徴があります。他にもサンプリング音源に比べ、ストレージ容量が節約できるといった利点もあります。
AASは、フィジカルモデリングを得意とするメーカーで、モデリング技術を活用した数多くの製品をリリースしています。
フィジカル(物理)モデリング音源製品の記事
 MODO BASS 2使い方(スライドなど)やレビュー!SE、無料版CSとの違いも解説!IK Multimediaベース音源
MODO BASS 2使い方(スライドなど)やレビュー!SE、無料版CSとの違いも解説!IK Multimediaベース音源  Pianoteq 8使い方やレビュー!Stage・Standard・Pro・Studioの違いも比較!MODARTTピアノ音源どれがおすすめ?
Pianoteq 8使い方やレビュー!Stage・Standard・Pro・Studioの違いも比較!MODARTTピアノ音源どれがおすすめ?  AAS「Strum GS-2」使い方やレビューとセール情報!物理モデリングギター音源の実力とは?
AAS「Strum GS-2」使い方やレビューとセール情報!物理モデリングギター音源の実力とは?  MODO DRUM 1.5使い方やレビュー!無料のCSやSEとの違いも解説!重いって本当?IK Multimediaのドラム音源
MODO DRUM 1.5使い方やレビュー!無料のCSやSEとの違いも解説!重いって本当?IK Multimediaのドラム音源  AAS「Lounge Lizard EP-4」使い方やレビューとセール情報!フィジカルモデリングエレクトリックピアノ音源
AAS「Lounge Lizard EP-4」使い方やレビューとセール情報!フィジカルモデリングエレクトリックピアノ音源 2. 導入するメリット
Ultra Analog VA-3を導入するメリットは以下の点が考えられます。
- アナログな太い音×比較的広い音作りができる
- 3つのエフェクトモジュールがある
アナログな太い音×比較的広い音作りができる

フィジカルモデリングなだけあってサンプルを元とするアナログシンセモデルのソフトシンセに比べると音作りの幅は広いです。
計4つのオシレーターに、4つのフィルターやエンベロープなどを操作することができ、エフェクトも含めてそれぞれを独立して操作することができます。
わかりやすくあらわすと
- VCO1→Filter1→Envelope1→VCA1
- VCO2→Filter2→Envelope2→VCA2
- VCO3→Filter3→Envelope3→VCA3
- VCO4→Filter4→Envelope4→VCA4
のように個々に独立して操作できます。もちろん組み合わせる事も可能です。
アナログの太い音を再現しながら、フィジカルモデリングによって他のアナログモデルのシンセより比較的音作りの幅が広く、いいとこ取りなソフトシンセです。
リードやベースだけでなく、エレピやクラビネット、オルガンなど鍵盤系やパッドの音なども太い和音で出せます。
3つのエフェクトモジュールがある

シンセの音作りだけでなく、エフェクトモジュールもそれぞれのレイヤーに1つずつと、共通のもので合計3つもあり、それぞれ最大5つエフェクトがかけられます。
独立したエフェクトモジュールがこれだけ搭載されているシンセは少ないと思います。
3. 利用する前に知っておくべき注意点・デメリット
しかしながらUltra Analog VA-3を導入する前に知っておくべき注意点、デメリットもあります。
- パラメータが独立しているので操作に注意
- 実機モデルではないバーチャルアナログシンセサイザー
パラメータが独立しているので操作に注意
細かく独立したパラメータがあるので、いじるパラメータを間違えないように気をつけましょう。
特にフィルターやアンプエンベロープは、共通しているシンセが多いので感覚的に間違えて操作しがちです。
よく間違えます、、
実機モデルではないバーチャルアナログシンセサイザー
Ultra Analog VA-3は実機を収録したサンプルではなくフィジカル(物理)モデリングのバーチャルなアナログシンセサイザーです。
もちろん、参考にした実機シンセサイザーはあると思いますが特定のモデルをエミュレートしていないので、実機モデルの再現度の高いシンセが欲しい方は注意が必要です。
太い音が出るので重宝しますが、個人的にはモデリングならではの高音域の鳴り方が少し気になりました。ただし、音作り次第で解消されると思います。
4. 口コミ・評判を紹介!
Ultra Analogの口コミ・評判をまとめました。
以前のバージョンから評価は高く、人気のシンセサイザーです。
AAS ULTRA ANALOG VA-3 で改善されたところ。
・音の質感
・プリセットの検索性
・レイヤー、スプリット対応
・ラダーフィルターの追加
・ピッチベンドの既定値が±2
AAS ultra analogおすすめやで
AAS Ultra Analog、個人的に推せる
前々から狙っていた AAS Ultra Analog VA-3
引用:Twitter
5. Ultra Analog VA-3に関するセール情報
AAS製品は、ブラックフライデーのみならずセールで安い場合があります。
Ultra Analog VA-3もセールで半額以下になる場合があり、最安ではSession版が無料配布され、そこからのアップグレードで3,300円で販売されました。
最新のセール情報はこちらをご覧ください。
 【毎日更新】DTMセール情報まとめ!無料配布やおすすめVSTプラグイン、音源、ブラックフライデー時期も解説!
【毎日更新】DTMセール情報まとめ!無料配布やおすすめVSTプラグイン、音源、ブラックフライデー時期も解説!  ソフトシンセ最新セールまとめ!おすすめプラグインの最安値や過去セール時期も解説
ソフトシンセ最新セールまとめ!おすすめプラグインの最安値や過去セール時期も解説  【随時更新】AASセール!過去最安値はここ!Ultra Analog、Strum、Lounge LizardなどApplied Acoustics Systemsプラグイン
【随時更新】AASセール!過去最安値はここ!Ultra Analog、Strum、Lounge LizardなどApplied Acoustics Systemsプラグイン 6. AAS製品のインストール・アクティベーション方法
Plugin Boutiqueにて解説されていますが、AAS製品のインストール・オーソライズ方法は簡単で以下の2STEPで完了します。
- https://www.applied-acoustics.com/package/でシリアルナンバーと名前、メールアドレスを入力
- 製品をダウンロード・インストール
7. 使い方を解説!
ここからは実際にUltra Analog VA-3の使い方を簡単に解説します。
英語の公式マニュアルはこちらをご覧ください。
プリセットは最上部もしくは、「Browser」のエリアで選択します。

左側で「Packs」「Sounds」「Categories」「Creators」でライブラリーの表示を切り替えて選択できます。
Editor

「Editor」エリアは「Modes」「Synth」「Effects」からなる2つの独立したエンジンと共通の「Effects」部分からなります。

上部で黄色部分「Layer A」緑部分「Layer B」それぞれのGainやPan、Tune、電源ボタンでオンオフできます。MasterのGainも調整可能です。
Modes

Modesは、アルペジエーターやレイヤー機能、マクロコントロールなど演奏やパラメータの設定ができます。
Clock:LFOとアルペジエーターモジュールのテンポをコントロールするために使用されます。「Host」でDAWと同期し、オフすると「Rate」でBPMを調整できます。
Keyboard:「Poly」ボタンでポリフォニックに、オフにするとモノフォニックになります。「Tune」は、チューニングを変更できます。
ボイス数は上部のSettingsから変更できます。
Unison:ボイスを重ねて演奏することができます。モジュールの左上にあるLEDをクリックすることでオンになります。各ボイスは、「Detune」を使用して、ピッチをずらすことができます。「Delay」は少しのタイムラグを加えます。
Glide:ノート間ですぐ移行せずスライドさせるために使用します。「Time」は、音程が 1 オクターブスライドするのに必要な時間を設定します。「Mode」メニューでは、「Constant(Const)」モードと「Proportional(Prop)」モードを選択することができます。Constantでは、音程のスライドに必要な時間は常に同じです。Proportionalに設定すると、スライド時間は2つのノート間の間隔の幅に比例します。「Legato」ボタンをクリックするとGlideは、最初のノートがリリースされる前に2つ目のノートが演奏された場合にのみ発生します。
Macros

4つのマクロコントロールを設定できます。「MODULATION」「TIMBRE」「ENVELOPE」「EFFECT」これらのモジュールは、上部Homeのマクロコントロールに対応しています。各マクロでは、最大4つの合成パラメータをアサインすることができます。各マクロの上部には、モジュレーション量を制御する「Amount」ノブがあります。Homeのマクロコントロールは、Amountノブで設定した量を基準に調整します。
MODULATION:モジュレーションマクロは、モジュレーション量をコントロールするために使用されます。通常、ビブラートやトレモロなどのパラメータがマッピングされています。
TIMBRE: サウンドのトーンを変更するために使用され、通常はシンセサイザーのフィルターモジュールのパラメータがマッピングされています。
ENVELOPE:サウンドの時間領域の特性を調整するために使用されます。通常、ADSRモジュールのパラメータがマッピングされます。
EFFECT:サウンドに適用されるエフェクトの量をコントロールすることができます。通常、各サウンドで使用されるエフェクトモジュールのパラメータがマップされています。
Vibrato:LFOでピッチモジュレーションを設定する必要がなくビブラートモジュールが用意されています。「Rate」は、ビブラート効果の周波数(周期)を0.3 Hz~10 Hzの間で設定します。「Amount」は、変化量を設定します。「Delay」は、少しラグがあるように調整することができます。「Fade」は、ビブラート効果をゼロからAmountで設定した量までフェードする時間を設定できます。
Arpeggiator

アルペジオパターンは「Range」「Span」「Order」の組み合わせで設定します。左上にあるLEDをクリックすることでオンになり、「Sync」ボタンでDAWと同期、オフにして「Rate」からBPMを調整、「Steps」で音価を設定します。
Range:パターンが繰り返されるオクターブ数を選択するために使用します。
Span:ドロップダウンメニューで弾いたノートを基準としたRangeの方向を設定します。下がる場合は「Low」に、上がる場合は「High」に、上下両方にする場合は「Wide」に設定できます。
Order:音符を演奏する順番を設定し、アルペジオパターンを決定します。「Fwd」に設定すると、最も低い音から最も高い音へと演奏されます。「Bwd」に設定すると、最も高い音から最も低い音へと演奏されます。「RnRx」「RnRi」では、音符は最低音から最高音に向かって順方向に演奏され、最高音から最低音に向かって逆方向に演奏されます。RnRiの場合は、逆方向に切り替える際に、最高音と最低音が2度繰り返されます。「Chord」は、すべての音が一度に演奏されます。
L:Lボタンをオンにすると、新しいノートが演奏されるまで、アルペジエーターはそのパターンを演奏し続けます。

リズムパターン:16ステップのパターン表示で、アルペジオパターンにリズミックパターンを追加することができます。対応するステップが選択される(赤ボタンがオン)とノートが演奏されます。表示のすべてのステップをオンにすると定期的に音符が演奏され、特定のステップのみを選択することでリズミカルなパターンが作成されます。各ステップの下にあるボタンは、そこでステップを終了し、始めに戻る設定です。
Split:2つのレイヤーを使用する場合、スプリットキーボードモードを有効にすることができます。緑と黄色に色分けされ、キーボードの左の部分はLayer Aに、右の部分はLayer Bに関連付けられています。分割するノート(Split Note)は、右端にある「・・・」からドロップダウンメニューで選択することができます。また、「Learn」からMIDIキーボードで任意のスプリットノートを設定することもできます。
Synth

Synthは、シンセサイザーの音作りができるエリアです。
VCO
アナログオシレーターの機能を備えたオシレーターモジュールです。ウェーブテーブルではなく精密なモデリングアルゴリズムでできてます。「VCO 1」「VCO 2」が2つのレイヤーにあり合計4つあります。
Shape:ドロップダウンメニューを使用して波形を選択します。Squareに設定されている場合、「PW」でパルス幅を調整することができます。
Octave / Semi / Detune:オクターブ / 半音 / 100で半音(最大300)でピッチを調整できます。
Sub:オシレーターのピッチより1オクターブ下の音を発生させるサブオシレーターです。

セクション下にある四角マークをクリックすると追加のパラメータが表示されます。
Ramp:オシレーターにはランプジェネレーターが搭載されており、キーを押したときにピッチの変化を得ることができます。Rampはオシレーターのスタート・ピッチを設定し、「Decay」はピッチがこのスタート値からノートのピッチまでの時間を決定します。「Amount」で、ノートに対して -72~+72の半音の間でピッチを設定することができます。
Hard Sync:Hard Sync(同期)にはマスターオシレーターとスレーブオシレーターが使用されます。マスターオシレーターの波形の各周期の最初にスレーブオシレーターからの信号がリセットされ再起動されます。同期モードでは、サブオシレーターノブはSyncノブになるため使用できません。

公式マニュアル引用
Filter

「1」「2」タブを切り替えて2つのフィルターなどのモジュールがあります。
フィルターは、ドロップダウンメニューで「Type」を選択することができます。「Order」で2×(ローパスとハイパスは-12dB/oct、バンドパスは-6db/oct)または4×(ローパスとハイパスは-24dB/oct、バンドパスは-12db/oct)に調整することも可能です。さらに、「Drive」のドロップダウンメニューで選択した異なるサチュレーションアルゴリズムをフィルターに適用することができます。「Frequency」でカットオフ周波数を調整し、「Resonance」でレゾナンスの量を調整します。フォルマントフィルターを使用する場合、Resonanceは母音(a/e/i/o/u)を切り替えるために使用します。
フィルターのFrequencyとResonanceは、異なるモジュレーションソースでモジュレーションすることができます。「Key」はキーボードのピッチによる変化量を調整するためのもので、「Env」は左隣にあるF Envモジュールでの変化量です。
VCA

フィルターなどの1、2モジュールには、それぞれVCA 1とVCA 2のアンプセクションがあり、完全に独立させておくことができます。
「Level」はアンプ全体のレベルを調整するために使用し、「Pan」はステレオフィールド内の音の位置を調整するために使用します。LevelとPanは、「Key」を使ってノートによって変化できます。+の位置ではC3を基準に高音にいくほど、ブーストもしくはRになります。低音にいくほど、その逆になります。

Noise:Noiseモジュールはホワイトノイズを発生させ、-6dB/Octのローパスフィルターでノイズの周波数を調整します。「Color」は、そのローパスフィルターのカットオフ周波数を変化させるために使用します。
LFO

LFOモジュールは、右側にある「VCO」「FILTER」「VCA」のモジュレーションソースとして使用されます。
Shape:LFOの波形はShapeドロップダウンメニューで選択します。LFOのレートは「Sync」でDAWに合わせた速さもしくは「Rate」で決定します。
R:キーボードで演奏される音を個別に制御することができます。ノートが演奏されたときにLFO波形をリセットします。
Phase:信号の位相を決定します。波形の全周期にわたって値を選択することができます。0〜100%(0~360度)で調整します。
PW:VCO同様にSquareに設定されている場合、パルス幅を調整することができます。
Fade:出力信号にフェードイン効果を加えることができます。
Delay:LFOの開始を遅延します。
Envelope

エンベロープは、「Filter Envelope(F Env)」と「Amp Envelope(A Env)」の2つのエンベロープジェネレーターが搭載されています。どちらも同じ性能です。標準的なADSR(Attack/Decay/Sustain/Release)を使用して生成されます。
Velocity:「Attack」からアタックタイムをMIDIから受信したベロシティ信号で調整し、ベロシティの増加に応じてアタックタイムを短くすることができます。
Exp:Exp ボタンがオフ場合は線形で、スイッチを入れると曲線を描きます。

公式マニュアル引用
Free:エンベロープのサスティーンをバイパスして、キーを押している時間に関係なく、ディケイからリリースに直接移行することができます。
Retrig:新しい音が演奏されたときにアタックフェーズから新しいエンベロープをトリガーします。オフの場合は、レガートした2つ目の音に、1つ目の音のエンベロープ信号を適用します。
Loop
3つのループモード「AD」「ADR」「Once」があります。キーが離されるまでエンベロープをいくつかのステージ間で循環させることができます。
AD:音符が離されるまでアタック(サスティーンレベルから)とディケイフェーズを繰り返します。
ADR:アタック、ディケイ、リリースのフェーズを繰り返します。
Once:エンベロープは通常通り演奏されますが、キーが離されるとエンベロープジェネレーターがアタックフェーズとリリースフェーズを繰り返します。

公式マニュアル引用
Effects

各レイヤーの出力にエフェクトモジュールがあり、レイヤーミキサーの後のシンセサイザーの出力にも1つあります。それぞれのエフェクトモジュールは同じ性能です。
左端をドラッグして順番を変更します。Compressor、Reverb、Equalizer以外の2つは中央にあるドロップダウンメニューを使って、以下のエフェクトにできます。
- Delay
- Distortion
- Phaser
- Vintage Chorus
- Chorus
- Flanger
- Auto Wah
- Wah Wah
- Notch
- Equalizer
- Compressor
- Guitar Amplifier
- Reverb
- Tremolo
Setting

Settingでは、チューニング、ポリフォニーボイスの数、ピッチベンドの範囲、外部マクロモジュールの割り当てなど、シンセサイザーの一般的なパラメータが固定されています。これらのパラメータの値は、すべてのサウンドに適用されます。
まとめ
Ultra Analog VA-3はアナログ感のある太い音で様々な音色を奏でることができるので重宝します。
ただし、あくまでバーチャルアナログシンセサイザーなので実機をモデルとした再現度の高いアナログシンセサイザーが欲しい方は注意が必要です。
この記事が参考になれば幸いです。
質問等ございましたらコメント欄からどうぞ!