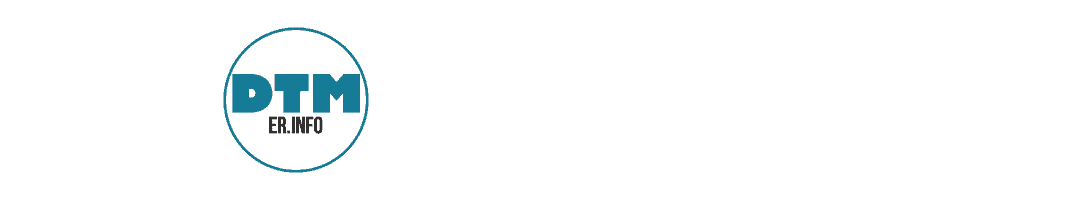Arturiaが開発するソフトシンセPigments v5がリリース!
Pigmentsはもともとアナログとウェーブテーブルを組み合わせたシンセサイザーでしたが、Pigments 2からサンプル、Pigments 3からハーモニックオシレーターやユーティリティエンジンも加わました。1→5へと音の太さなど確実に強化されており、個人的にもどんどん好きなっていくシンセです。
この記事では、Pigmentsが他の定番ソフトシンセと比較してどう違うのかをレビューします。また、導入するメリットや注意点、インストールやアクティベーション方法、使い方も解説。
この記事を読めば、Pigmentsに関する基本的な情報は全てを揃いますので、ぜひ参考にしてください。
ソフトシンセに関するまとめ記事はこちらをご覧ください。
 【随時更新】ソフトシンセおすすめ最新23選と比較!最強はどれ?人気プラグインの使い方まで解説
【随時更新】ソフトシンセおすすめ最新23選と比較!最強はどれ?人気プラグインの使い方まで解説 1. Arturia「Pigments 5」とは?
Pigments 5は、Arturia(アートリア)が開発するソフトシンセPigmentsのVersion 5です。
- アナログ
- ウェーブテーブル
- サンプル
- ハーモニック
4種類のオシレーターをもとに、わかりやすいかつ豊富なモジュレーションソースで扱いやすいにも関わらず変化する自由なサウンドを構築できます。曲を決定づけるような中心となるサウンドを奏でることができ、アバンギャルドな音作りが可能でありながら、説得力のある太さあるサウンドに仕上げることができます。
また、同社のV Collectionシリーズで培ったアナログシンセのエミュレートやエフェクトシリーズFX Collectionの名機モデルエフェクトも内蔵されています。
作曲ソフトDAWの拡張機能VST、AU、AAXプラグインとして利用できNative Instrumentsのコントローラーなどと連携するNKSにも対応していますが、単体での起動(スタンドアローン)も可能です。
| 開発会社 | Arturia(アートリア) |
| 操作画面 |  |
| 製品名 | Pigments 5 |
| 主なオシレーターの種類 | アナログ/ウェーブテーブル/サンプル/ハーモニック |
| 価格(定価) | 199ドル Splice Plugins 9.99ドル / 20ヶ月 |
<補足>ウェーブテーブルとは?
初代ウェーブテーブルシンセサイザー「PPG WAVE」(2.2と2.3があります)
ウェーブテーブルは複数の波形形状を含むテーブルを使用して音を作る方式です。
あらゆる波形を合成し、波形間をモジュレーションできるのでアナログシンセサイザーと違いオシレーターの種類が豊富で細かくエディットできる点が特徴です。
 Waldorf「PPG 3.V」使い方やレビューとセール情報!名機ウェーブテーブルシンセモデルソフト
Waldorf「PPG 3.V」使い方やレビューとセール情報!名機ウェーブテーブルシンセモデルソフト Arturia Pigments 5 ▶︎Plugin Boutique ▶︎ADSR Sounds ▶︎Best Service ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎サウンドハウス ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
▶︎Plugin Boutique ▶︎ADSR Sounds ▶︎Best Service ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎サウンドハウス ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
PigmentsはSplice Pluginsにて月額払い(Rent-to-Own / 借りる→自分のものに)でも利用可能です。Splice Pluginsに関する詳しい記事はこちらをご覧ください。Splice Pluginsは通常の月額払いと違い、支払いの義務はなくいつでも停止そして再開することが可能です。
 Splice Plugins使い方!Serumなど月額サブスク(Rent-to-Own)で使えるプラグイン&DAW
Splice Plugins使い方!Serumなど月額サブスク(Rent-to-Own)で使えるプラグイン&DAW 2. Pigments 5のアップデート点・新機能(4との違い)
Pigments 5のバージョンは、無償アップデートです。すでにPigmentsをお持ちの方であれば誰でもアップデートできます。
以下のようなアップデート点・新機能があります。
CPU消費量の削減・重さを軽減
PigmentsはマルチコアプロセッシングによりCPU効率を向上させ、より多くのユーザーがこのパワフルなソフトシンセを簡単に使用できるようになりました。
1クリックであらゆるサウンドをメロディ化
新しいジェネレイティブシーケンサーは、ワンクリックシーケンス生成と新しいプレイモード、保存可能なプリセット、シーケンスブラウズを備えています。シーケンサーロックを使えば、どんなサウンドにもシーケンス設定を適用できます。
Pigmentsであらゆるオーディオを処理
ユーティリティエンジンから、トラックサイドチェイン入力を通してインストゥルメントにサウンドをルーティングすることで、Pigmentsで外部オーディオを処理できるようになりました。追加のFXルーティングオプションも統合されました。
より優れたシンセシス
Pigments 5の新しいウェーブテーブルとサンプルのセレクションで、サウンドを作る方法がこれまで以上にあります。
スタイリッシュに作曲できるGUI
Pigmentのリフレッシュされたインターフェイスには、新しいビジュアライザーやその他のUXの強化とともに、改善されたPlayビューが含まれています。
3. 導入するメリット
実際に使ってみて次のようなメリットがあると考えます。
- 使いやすい
- 充実した選びやすいプリセット
- アナログ感や太さも出せる
- 変化するサウンドや複雑な音作りも魅力
使いやすい

他のソフトシンセをある程度使ったことがある方であれば、初見でもかなり使いやすいでしょう。
PigmentsはLFOやENVELOPE部分などモジュレーションが特にわかりやすく、発音するとリアルタイムで動くので、どのパラメータがどこにアサインされているかわかりやすいです。バージョン4から、モジュレーションのエディットがさらに簡単になり個人的には操作性、使いやすさはNo.1と言っても過言ではありません。

また、Pigmentsを起動して左上からTutorialもありますので、英語ですが操作しながらチュートリアルをうけることが可能です。
エディットをあまり必要としない場合も、Playビューで簡単に重要な操作だけ行うことも可能です。
充実した選びやすいプリセット

充実した1571ものプリセットがあります。
プリセットは上部の名前部分を選択してカテゴリーでから選ぶことも可能ですが、上部の本棚マークからExploreを開いて選ぶことも可能です。
Exploreでは、ジャンルやスタイル、タイプなどでソートすることが可能なだけでなく、プリセットを選択すると右下に使用されているオシレーターエンジンやフィルタータイプまで表示されかなり便利です。Storeからプリセットを追加購入することも可能です。
アナログ感や太さも出せる

アナログのオシレーターがあることはもちろん、フィルターなどにも同社ArturiaのV Collectionシリーズで培ったアナログシンセのエミュレートが活かされています。また、同社のエフェクトシリーズFX Collectionの名機モデルエフェクトも内蔵されています。
もちろんデジタルなサウンドも出せますが、太いサウンドを出すことが可能です。バージョンアップするごとにより太いサウンドになってるように感じます。
変化するサウンドや複雑な音作りも魅力
多様なモジュレーションソースやシーケンサーを使って、扱いやすいにも関わらず複雑なサウンドも自在に作成できます。曲を決定づけるような中心となるサウンドを奏でることができ、アバンギャルドな音作りが可能でありながら、説得力のある太さあるサウンドに仕上げることができます。
4. 利用する前に知っておきたい注意点・デメリット
しかし導入前に知っておくべき注意点が2点あります。
- 重い?バージョン5で軽くなった?
- ジャンルによっては、他の製品が良い場合も
注意点1. 重い?バージョン5で軽くなった?
バージョン5になり、CPU負荷が軽減されました。しかし、実際に使ってみると、音作りによりますがまだ軽いとは言いづらくある程度、負荷がでる場合もあります。パソコンのスペックに自信がない方はお気をつけください。
注意点2. ジャンルによっては、他の製品が良い場合も
同じくサンプル、グラニュラーにも対応したかなり多機能なソフトシンセとしてAvengerやFalconが挙げられます。それぞれの主な特徴は以下のような感じです。
Avengerの特徴
- 音の口コミ・評判No.1音が良いと定評がある
- 超多機能
- 使い方が難しい
Falconの特徴
- 他の様々な音源を起動するプラットフォーム
- 超多機能
- 使い方が難しい
EDMなどダンスミュージックで使える音を求めているのであればAvengerの方が使えるプリセットは多いと思います。Falconは、UVI Workstationで起動できる音源を全て起動できるプラットフォームでもあるのでUVI製品などをたくさん持っている方であれば持っておくべきでしょう。
ただし、Pigmentsと比較するとどちらも使い方はかなり難しいです。
 ソフトシンセ「VPS Avenger 2」使い方やレビュー!インストールやアクティベーション方法まで解説!
ソフトシンセ「VPS Avenger 2」使い方やレビュー!インストールやアクティベーション方法まで解説!  UVI「Falcon 3」使い方やレビュー!万能な超多機能ソフトシンセ&プラットフォーム
UVI「Falcon 3」使い方やレビュー!万能な超多機能ソフトシンセ&プラットフォーム 5. 口コミ・評判を紹介!
Pigmentsの口コミ・評判をまとめました。
バージョンがあがるたびに評価はうなぎのぼりです。
せっかくアップデートしたのだから、とこんな時間ですが「Pigments5」を触り出し。結論:DigitoneでもSH-4dでもOperatorでも、そしてPigmentsでも「俺の作る音色は同じ」。でも良いPluckと似非Epの音が出るシンセは良いシンセ。
Pigments 5というよりかは一緒に発売されたBeats Explorationsのプリセット結構好みかも。
プリセットに過剰に含まれている余計なライザーとかも比較的抑えめでLoFi、チルいフューチャーベースとかに使えそうな音色で
さっそくPigments 5試運転。新機能のランダムシーケンス鳴らしてみた。
オシレーター増えたりしたわけじゃないけど表示が微妙に変わったりして視認性が上がってる😊
あべんじゃも良いけどやっぱりぴぐめんも良いシンセだなー😃
arturiaサイトにログインしたら会員価格で69ドルだったのでPigments 5買ってしまいました。年始早々だけれど今年一なシンセかもしれない!
引用:Twitter
6. Pigmentsに関するセール情報
Arturia製品は、ブラックフライデーのみならずセールをおこないます。
割引率もそこそこ高く、半額ほどになる場合が多いです。Pigmentsもセールの対象になることがあります。
最新のセール情報はこちらの記事をご覧ください。
 【随時更新】Pigments 5セール!過去最安値はここ!Arturiaブラックフライデーやクロスグレード・アップグレードも解説
【随時更新】Pigments 5セール!過去最安値はここ!Arturiaブラックフライデーやクロスグレード・アップグレードも解説  【毎日更新】DTMセール情報まとめ!無料配布やおすすめVSTプラグイン、音源、時期やブラックフライデーも解説!
【毎日更新】DTMセール情報まとめ!無料配布やおすすめVSTプラグイン、音源、時期やブラックフライデーも解説! 7. Arturia製品のインストール・アクティベーション方法

Arturia製品のインストール・オーソライズ方法は、以下の4STEPで完了します。
- Arturiaでアカウント作成・ログインします。
- 右上人型アイコンの「MY ACCOUNT」→「Register New Product」からSN(シリアルナンバー)、UC(アンロックコード)を入力して登録します。
- ASC(Arturia Software Center)をダウンロード・インストールします。
- ASCを起動してログインし、製品をアクティベート・インストールします。
8. 使い方を簡単に解説!
ここからは実際にPigments 5の使い方を簡単に解説していきます。
公式の日本語のマニュアル(v4)が出ていますので、がっつり知りたい方はこちらをご覧ください。

Pigmentsは上部にプリセット、上部右側からPlay、Synth、FX、Seqの4つの項目に別れています。
音作りの中心となるシンセサイザー部分であるSynthから解説します。
ENGINE

左上ENGINE部分にENGINE1、ENGINE2のオシレーターがあります。それぞれ電源部分でオンオフ、下矢印からオシレーターの種類を
- Analog
- Wavetable
- Sample
- Harmonic
から選択でき、Copy Engine ◯からもう一方のENGINEにコピー、with modulationsでモジュレーションごとコピーします。
TUNE・UNISON

TUNE
ENGINEの左側にTUNE、UNISONがあります。
Coarse:半音ごとにピッチを調整できます。
Fine:半音の1000分の1単位でピッチを変えます。
鍵盤マーク:シンセに音程が反映されます。ドラムなどでオフにすることもできます。
Q:クオンタイズモードです。クオンタイズモードでは、モジュレーションにアサインした音程を制限して発音されるようになります。鉛筆マークから鍵盤が表示され、いらない音程をクリックして消すことができます。
UNISON
名前部分をクリックしてClassic、Chord、Super3つのモードから選択できます。ただしサンプルオシレーターやハーモニックオシレーターでは別のオプションとしても機能します。
Voices:ユニゾンのボイス数を調整できます。
Detune:ユニゾンのボイス間にデチューンを加えます。
Stereo:ユニゾンのボイスに広がりを加えます。
Phase:ユニゾンボイスの位相を調整できます。
ここからは、各オシレーターの種類について解説します。
Analog

3つのオシレーターからなるアナログシンセサイザーのエミュレートです。
OSC1〜3
左から順に以下のパラメータがあります。オシレーターによって備わっているパラメータが若干異なります。
Sync:OSC 2とハードシンクします。
Key(鍵盤マーク):音程を反映させます。オフにすると音程が一定になります。
Coarse:半音ごとにピッチを調整できます。
Fine:半音の1000分の1単位で細かなピッチを調整できます。単位をSemitonesもしくはHertzから選択可能です。
波形マーク:オシレーターの波形を選択できます。
Width:三角波、矩形波のパルス幅を調整できます。
Volume:それぞれのオシレーターの音量を調整できます。
FM:FM(周波数変調)を有効にします。OSC 1、2のFMボタンから線で繋がっているノブで適用量を調整できます。
MODULATOR:FMのソースとしてOSC 3とノイズをミックスして調整できます。

ENGINE 〇:MODULATORの名前部分を選択してFMのソースとしてもう片一方のエンジンを使用することも可能です。もう片方のオシレーターがアナログの場合、FM Amtで適用量を調整、Noiseでノイズソースのレベルを調整、CoarseとFineでピッチも調整できます。サンプルやウェーブテーブルの場合はサンプル選択や位置(Start、Position)を選択でき、Harmonicsの場合はRatioで倍音の比率を調整できます。

OUTPUT
Filter Mix:FILTER1、2どちらに反映させるかをパーセンテージで決めることができます。
Volume:ENGINE全体の音量を調整します。
NOISE
Color:Red、White、Blueからなるノイズカラーを調整できます。
Volume:ノイズレベルを調整できます。
Wavetable

ウェーブテーブルは、左上からプリセットのWaveformを選択できます。Waveform選択画面右上のフォルダマークや波形マークから自分の波形をインポートすることも可能です。右側立方体マークで波形の表示を変更します。右側のOUTPUTはAnalogと同じ仕様です。
Morph:モーフィング機能でオンの場合ウェーブテーブル間をスムーズに移動します。
Position:ウェーブテーブルの位置を調整します。これは3D波形にするとわかりやすいです。
Volume:ウェーブテーブルオシレーターのボリュームを調整できます。
ここからは下部の波形を変化させる部分に解説しますが、これらは2Dにすることで波形の変化がよくわかります。それぞれ〇〇 Modから右側のモジュレーター(もしくはエンジン)をソースとしたモジュレーション量を調整できます。
FREQ MOD(FM) / RING MOD
FM(Frequency Modulation)はリニア(Linear)とエクスポネンシャル(Exponential)から選びます。リニアの方が基音が動かずどちらかと言うとナチュラルなのに対してエクスポネンシャルは基音ごとアバンギャルドに変化します。リングモジュレーション(Rig Mod)も新しく搭載されました。
PHASE MOD
以下4種類の設定ができる位相モジュレーションです。
- Key:MIDIノートでウェーブテーブルの位相がリセット
- Random:MIDIノートでウェーブテーブルの位相がランダムにリセット
- Self:メインのCoarse、Fineに従って位相がリセット
- Mod Osc:モジュレーターの位相が0にリセットするたびウェーブテーブルもリセット
PHASE TRANSFORM
7種類のTypeから波形を選択し、その波形に応じてソース波形がねじ曲がります。波形によってパラメータの名前は変わりますが、Typeの左側にあるノブで変化量を調整できます。
WAVEFOLDING
波形のピークを折りたたむようにして変化させます。Shapeから3つの曲げ方を選択でき、曲げる量をFoldから調整できます。
MODULATOR
上記の波形加工する4つのパラメータの追加モジュレーターとして機能します。10の波形から選択でき、Volumeでレベル、TuneとFineでピッチを調整できます。アナログオシレーター同様にもう片方のエンジンをソースとして利用することも可能です。
Sample
v2で新たに追加されたSampleはA〜Fまで6つのスロットがあります。それぞれを選択し、Wavetable同様に左上からサンプルを変更できます。右上からMain、Edit、Mapの3つのページが選択できます。
MAIN(GRANULAR)

MAINには下部にGRANULARがあります。電源ボタンをオンにすることでサンプルが分散して発音されます。
Density:分散させる速さ(密度)を決めます。Hertzでヘルツ、Straight、Triplets、DottedでBPMに合わせた通常、三連、付点の速さで調整できます。
Shape:分散した発音のエンベロープタイプを選択できます。
Size:分散させる長さを決めます。
下部には左から以下のランダム性を加えるパラメータがあります。パラメータによっては、矢印マークを選択してプラスの向き or マイナスの向き or 両方も設定できます。
Start:スタート位置にランダム性を加えます。右側真ん中にある開始位置を決めるStartノブが基準となります。
Pitch:分散のピッチにランダム性を加えます。
Density:新しいグレインが生成される速度にランダム性を加えます。
Direction:分散の方向にランダム性を加えます。
Size:グレインの長さにランダム性を加えます。
Pan / Width:左右のパンニングや広がりにランダム性を持たせます。
Volume:グレインのボリュームにランダム性を加えます。
EDIT

ここからサンプルをエディットできます。
TUNE:サンプルのピッチとルートノートを設定できます。
PLAYBACK:サンプルの再生を調整できます。Play Modeで、通常とリバース再生(Normal / Reverse)を設定できます。ループボタンからループをオンにすると、Loop Modeでループを前方向のみ(Forward)、逆再生あり(Back & Forth)から設定できます。Rボタンをオンにすると、エンベロープのリリースしている間もサンプルはループし続けます。Loop Fadeでは、ループクロスフェード量を調整できます。
MIX:パンニングとゲインを調整できます。
SLOT ◯:他のスロットにコピーしたり、サンプル削除や選択範囲をリセットすることも可能です。
MAP

ここでA〜Fまで複数サンプルをどう発音するか設定できます。
Single:単純にスイッチでサンプルを変えることができます。
Sample Pick:パラメータでサンプルを変化できます。
Key Map:キーによってサンプルを変化できます。Key/Velo Mapではベロシティで制御することも可能です。
Round Robin:サンプルを巡回させます。
Random:ランダムにサンプルを変えます。
UNISON

サンプルオシレーターの場合、ユニゾンはResonatorエフェクト、BitCrushエフェクト、Modulation(Freq ModとRing Mod)としても機能します。
Harmonic

v3で新しく登場したハーモニックオシレーターです。倍音をコントロールして音色を調整できます。真ん中下部のハイパス・SPECTRUM A・SPECTRUM B・ローパスでハーモニクスを変化できます。音を鳴らしながらパラメータをいじるとわかりやすいかと思います。
PARTIAL:右側真ん中にあるこのパラメータは数字部分を選択して、リミットを決めPartial(倍音)の数を調整できます。
FREQ MOD / PHASE MOD:Ratioで倍音の比率を調整し、他のオシレーター同様にモジュレーター(もしくはエンジン)をソースとして変調できます。
Morph:SPECTRUM A、SPECTRUM Bをブレンドできます。
Tilt Offset:Tiltが有効になる部分を調整できます。
Tilt:倍音減衰の傾きを調整できます。
Parity:倍音の奇数と偶数を調整できます。
Depth:変化量を調整できます。
Section:変化させる位置を選択できます。
倍音のステレオ位置を変化させる3つのモードがあります。
SPLIT:Odd、Even(偶数 / 奇数)を分けて左右にパンニングできます。
RANDOM:Rateで調整できる移動時間で、ランダムに倍音のステレオ位置が変化します。Depthで広がりの深さを調整できます。
PERIODIC:それぞれの倍音が周期的に変化します。Periodsで周期を調整でき、Depthで広がりの深さを調整できます。

他のオシレーターではユニゾンとして機能する部分は、倍音をコントロールできる3つの機能が選択できます。
WINDOW:選択したPosition、Win Size(範囲)の倍音のGainを調整できます。右下のノブからは選択範囲のFMモジュレーション量を調整できます。
CLUSTER:Position、Partialsで設定した部分的な位置の倍音数をDensityで密度を調整し、Clusters分の塊にします。倍音を見るとギュッと圧縮されているのがわかると思います。
SHEPARD:WINDOWに似ていますが、Phiで選択した範囲を変化することができます。
UTILITY ENGENE

シンプルなノイズ2つとオシレーター1つの追加エンジンです。それぞれ左側でFilter Mix(Filter 1/2に送る量)とVolumeを調整できます。
NOISE 1/2
ノイズは、真ん中名前をクリックしてサンプルを選択できます。
Key:リトリガーモードをKeyもしくはRandomから選択できます。
ループマーク:ループ再生します。
Length:長さを調整できます。
鍵盤マーク:キーに追従します。
Tune:ピッチを調整できます。
Filter:LP(ローパス)、HP(ハイパス)フィルターを調整できます。
OSCILLATOR
オシレーターはAnalogとほぼ同じようなパラメータで設定できます。
オシレーターのOutputは
- Filters
- FX Bus A
- FX Bus B
- Direct Out
から選択できます。
FILTER

フィルターは2つありそれぞれのフィルター表示左下からバンドのタイプ(Mode)を選べるだけでなく、上部からSEM、Matrix 12、Mini Moog、Jup-8などV Collectionでエミュレートされた名機のフィルターが選択できます。選択されたフィルターによってパラメータは異なります。
KBD:鍵盤のキーによってフィルターが変化します。
Volume:フィルター出力のボリュームを調整できます。
Pan:フィルター出力のパンニングを調整できます。
FILTER ROUTING:フィルターのルーティングをそれぞれ別々のFXに送るSplitと直列・並列をブレンドするPre-FX Sumから選択して調整できます。
AMP MOD:ソースを選択してAMPをモジュレーションすることが可能です。ここは通常ベロシティが選択されており、これによりベロシティによって音量が変わることになります。
Voice Pan:ボイスパンニングを調整できます。
Send Level:エフェクト(FX)に送るセンド量です。
FX

エフェクトはFX A、FX B、AUXの3つに分かれており、それぞれ3つまで計9つのエフェクトが可能です。18種類のエフェクトがあり、JUNO-106のコーラスやBL-20 Flangerなど名機エフェクトもあります。
左側INSERTからBUS A、Bの音量、順番を選択できAUXは送る量(Send)、出力量(Return)を調整できます。
Seq(Sequencer)

シーケンサー、アルペジエーターを設定するエリアです。左上電源ボタンでオンオフArpeggiator、Sequencerを選択します。右側でPITCHはもちろんVELOCITY、OCTAVEなど各値をステップごとに上下にドラッグして調整できます。DIVは、各ステップの発音数を調整できます。
PLAYBACK
Rate:シーケンサーのスピードを調整できます。BPMやSync(DAWと同期した拍数)など右下から分解能を設定できます。
Swing:スウィング量を調整できます。
Mode:シーケンサーの進行方向を前(Forward)、後ろ(Backward)、前後(Forward & Backward)、ランダム(Random)から選択できます。
Polymetry:ピッチやベロシティ、オクターブなど各パラメータに独立した長さを持たせることができます。
Reset:ポリリズムを使用している場合、すべてのトラックがステップ1にリセットされるまでの小節数を設定できます。
GENERATION
シーケンサー生成するv5の新機能です。サイコロをクリックすることで次々生成することが可能です。
スケール:サイコロ上部のメニューでは、シーケンスを生成または編集する際にノートのピッチをクオンタイズするスケールを選択します。
チェックマーク:シーケンサーの現在のランダムな値が正規の値に変換されます。
磁石マーク:ノートをアクティブなスケールに強制的に合わせます。
Auto Regen:シーケンサーランダム機能用の新しいランダム値セットを所定の割合で自動的に生成します。
モジュレーションアサイン方法

真ん中にあるENVやLFOなどにパラメータをアサインするには、いくつか方法があります。
アサインしたいパラメータを先に選択する場合
- アサインしたいノブをクリックして右上+ボタンを選択
- モジュレーションソースを選択して上下にドラッグしモジュレーション量を調整

モジュレーションソースを先に選択する場合
- モジュレーションソースの名前部分を選択
- アサインしたいノブの周り部分(モジュレーションソースの色で光ります)を上下にドラッグしてモジュレーション量を調整
※モジュレーションソースをドラッグ&ドロップしてもアサインできます。
モジュレーションソースの名前部分をクリックすると、アサインした各パラメータが表示されモジュレーション量や電源ボタンでバイパス、×で削除の他にサイドチェインなどの設定も可能です。
KEYBOARD

ピンク色のモジュレーションソースは左から、ベロシティ(Velo)、アフタータッチ(AT)、モジュレーションホイール(MW)、MIDIノート(KBD)、MIDI Expression(EXP)によって変化できます。
ベロシティ、アフタータッチ、キーボードによる値は右側の線から自由に調整できます。
PITCH BEND:ピッチベンドの範囲をUp / Downで調整できます。Releaseに影響するかどうかオンオフすることも可能です。
PLAY SETTINGS:ボイス数や音を維持するHold、キーの移行時間を設定するGlide Timeを設定できます。Alwaysはオンにすると常にグライドし、オフにするとレガートした場合のみグライドします。
VOICE SETTINGS:新しいボイスが発音されるRotateと、最後に演奏された音に優先的に割り当てられるReassignから設定できます。
ENVELOPE

オレンジ色部分のエンベロープは左端がVCAになります。通常のADSRとアタック、ディケイのCurveが調整できます。ディケイとリリースはリンクする(リリースパラメータなし)ことができます。Retrig Sourceは、エンベロープのリトリガーとなるソースです。
LFO

黄色部分のLFOは、Waveformで波形を変化させ、Rateで速さ、Symmetryで対称部分をストレッチ、Phaseで開始位相を調整できます。画面が変化するのでわかりやすいです。Retrig Sourceでトリガーとなるソースを選択し、通常のBipolar(±)ではなくUnipolar(+のみ)にすることも可能です。
FADEから3つの追加セッティングが選択できます。
- Fade:トリガー時に、フェードインを適用します。
- Keytrack:鍵盤のノートによってLFOを変化させます。
- Smooth:LFOの波形を滑らかにします。
FUNCTIONS

緑色部分のファンクションでは、LFOとENVELOPEモードを選択し、Draw Modeなどを使って自由に描くことができるモジュレーションです。
RANDOM

ランダムに変化させるモジュレーションで上部から3つのタイプを選択できます。
COMBINATE

SourceとModを選択してAmountで量を調整し、2つの値をコンビネーションさせます。Typeから様々なコンビネーション方法が選べますが、画面が変化するのでコンビネーションによってどのように値が変化したかわかりやすいです。
MACROS

複数パラメータを一度にコントロールできるマクロコントロールです。モジュレーション同様にアサインでき、名前部分をダブルクリックして変更することも可能です。
Arturia Pigments 5 ▶︎Plugin Boutique ▶︎ADSR Sounds ▶︎Best Service ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎サウンドハウス ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
▶︎Plugin Boutique ▶︎ADSR Sounds ▶︎Best Service ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎サウンドハウス ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
まとめ
Pigmentsはv1は評価も高くなく薄い音の印象でしたが、v2、v3、v4、v5と確実に進化し他の定番シンセと比較しても全く負けないソフトシンセになったと思います。
個人的にはアバンギャルドな音をたくさん作りたくなるシンセだと思います。
この記事が参考になれば幸いです。
Arturia Pigments 5 ▶︎Plugin Boutique ▶︎ADSR Sounds ▶︎Best Service ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎サウンドハウス ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
▶︎Plugin Boutique ▶︎ADSR Sounds ▶︎Best Service ▶︎Splice Plugins(月額払い) ▶︎サウンドハウス ▶︎楽天 ▶︎Amazon ▶︎Rock oN ▶︎公式
質問等ございましたら下部のコメント欄からどうぞ!